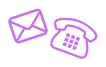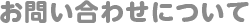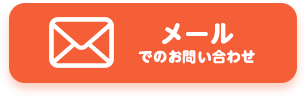公認心理師がいる教室

「今回の報酬改定がもたらしたこと」
今年の法改正は、令和6年4月1日の告示前から多くの事業所がその対応に振り回されました。当教室も個別支援の報酬単価が下がるという通達を受け、職員と協議し、その下がり幅によっては事業の方針自体の転換を考えなければならないほど悩みました。結果として、報酬単価自体は下がりましたが、新設された「子育てサポート加算」「家族支援加算」等の加算を活用すれば、個別支援を継続できない程の下がり幅ではなかったため、引き続き個別支援を継続しております。
昨今の共働き家庭の増加から、長時間の預かり支援にニーズがあるため長時間支援を優遇する方策は理解が出来ます。しかし、長時間支援を優遇するために1時間の支援を冷遇する措置となっては、支援の多様性が失われることにも繋がります。そもそも預かりの支援と、個別の支援では支援の方向性が全く異なるため、時間の長短で支援の質を図るものではありません。個別の支援内容を1時間から3時間に増やしたところで効果が3倍になるわけではありません。子どもの集中力を考えたらせいぜい、30分~45分が限界です。
だからこそ、個別は1回1時間の中に、その子に必要な要素をどれだけ絞って集中できるのか、必要なやりとりの試行回数をどれだけ稼げるか等の密度の高い支援を行うのです。
「小学校教員が求める療育」
元小学校の一担任として、放デイに求める支援は「集団の中で出来ない支援をやってほしい」に尽きます。これは勉強であれ、人との関わりであれ、担任の立場として中々一人の児童に対して、個別に関わってやれる時間がないからです。以前、私が3年生を担任した時に2年生の学習が十分に身についていない子がいました。
かけ算の九九が出来ないのだから、わり算の学習が出来るわけがありません。ですが授業の進度は決まっており、その子の理解は関係なしにどんどん授業は進んでいきます。そして、その子はやがて算数そのものを理解する事を諦めて、授業中に寝るようになりました。
その時その子に必要な支援はかけ算を最初から丁寧に教えてあげて、その子なりの出来る実感や自己肯定感を高めてあげることでした。しかし、課題も解決策も分かっているのに出来ませんでした。もちろん私の指導力不足もあったのですが30,40人を相手に毎日授業を行う中で「一人に」「時間をかけて」「分かるまで教える」ことが担任一人では物理的に不可能だったからです。
だからこそ、放デイのような事業所で、3年生ではあっても2年生の学習を、その子のためだけに、時間をかけて教えてあげることができたら、それは何て素敵なことだろうと思い、私はこの教室を立ち上げました。
「これからの放課後デイ」
今年度の法改正の影響を受けてなのかは分かりませんが、今年から児童発達支援から放課後デイの受給者証への取得が難しくなりました。市単位かと思ったのですが、様々な市でも同様の基準になっていました。ざっくりまとめると、こんな感じです。
①療育手帳又は児童相談所の判定証明を取得している
②医師の発達障害相当の診断書かつ療育の必要性ありの記載
③支援級、支援学校への就学が確認できること(通級は不明)
児童発達支援から放課後デイへ受給者証の種類が切り替わるため、再度上記の要件のどれか1つを満たしてください、ということです。これは結論を端的に述べると、定型発達のお子様と比べ個別のサポートは必要ではあるが、通常級に配置できる程度のお子様は放課後デイに通うことが難しくなるということです。
例えば、療育手帳の取得要件の際に、よく行われる田中ビネー知能検査というものがあります。こちらは知能指数をIQという形で100を平均として算出し、概ね70を下回った場合が軽度の知的障害相当の判定となるため、療育手帳取得の条件となります。しかし、この数値は私自身も田中ビネーを何度か行ってきましたが、ある程度「椅子に座れる」「大人と会話のやり取りが出来る」「3分程度課題に向き合える」お子様であれば、70を下回る事はありません。そのため、上記の要件は満たしているけれど、「多少の言葉の遅れがある」「指示や理解の遅れがある」「取り組みや作業の速さが遅い」等の特性が見られるお子様は、70を下回る程ではないけれど、70~90程度の所謂グレーゾーンという分類になります。つまり、小学校の通常級で全体の輪の中に居ることはできるけれど、学習やグループ活動の参加等には個別の配慮を必要とする層になります。
そのため、上記のお子様たちが放課後デイの要件を満たせず、受給者証を取得できないまま就学した場合、今まで児童発達支援で受けられていたような公的サポートが受けられず、自助努力で対応せざるを得なければなりません。これは親の立場としても、急に梯子を外されたような感覚になるのではないでしょうか。もちろん、小学校就学時に再度、要件を定めて利用児童のスクリーニングをかける必要はあります。しかし、小学校就学という定型発達のお子様であっても環境の変化が大きく、学習不振や不登校のリスクが高いタイミングで、放課後デイの利用が出来ません、というのは、適切な保護者支援とは言えないと思います。せめて就学後1年間は暫定的に仮受給者証を発行し、1年間の登校状況、学習への取り組みの様子を見てから知能検査や、医療機関の診断相当のスクリーニングをかける方が、まだ納得ができると思います。
言い換えれば、多少勉強の遅れはあっても学校には前向きに通えている、お友達とも多少トラブルはあっても、いじめや仲間外れ等の生活に支障が出るほどのリスクがなければ、通常級でも通じるという証拠になります。
ただ、現状そういった措置が国から急に出るとも思えないので、これから放課後デイへの受給者証を取得しようと思ったら、現実的な方法は保護者がいかに療育の必要性を認めてくれる病院やクリニックを見つけて、診断書を取得できるか、ということになります。
小学校の学級担任としても、通常級の支援が必要なお子様たちに支援が広がってほしいのに今回の改定はそういった子達をより締め出すことに繋がっていることに、いつか国は気づいてくれるのか、それともインクルージョン(包括的支援)の推進、という名のもとに学級担任に全ての責任を押し付けるのか、、、明るい兆しが中々見えないのが現状です。
最後はただのぼやきとなってしまいましたが、今後も気づいたことや感じたことなどを時間を見つけて発信できたらと思います。ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
ご利用に関する疑問や質問などありましたら、お気軽にお問い合わせください。