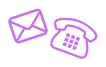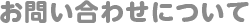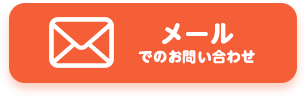公認心理師がいる教室

令和6年度報酬改定についての解説
今回の質問
「報酬改定って何? 保護者への影響はあるのか?」
 今年は、児童発達支援・放課後等デイサービスの管轄が厚生労働省からこども家庭庁に移り、また3年に1回程度行われる障害福祉サービス等の報酬改定の年度も重なったことにより、福祉事業所にとっては今までにない変化の激しい年度となりました。療育業界大手のK社の民事再生手続きや、L社の個別支援から長時間預かりへの方針転換等、ニュースや実際に通われている親御様の間で話題になったかと思います。
今年は、児童発達支援・放課後等デイサービスの管轄が厚生労働省からこども家庭庁に移り、また3年に1回程度行われる障害福祉サービス等の報酬改定の年度も重なったことにより、福祉事業所にとっては今までにない変化の激しい年度となりました。療育業界大手のK社の民事再生手続きや、L社の個別支援から長時間預かりへの方針転換等、ニュースや実際に通われている親御様の間で話題になったかと思います。
では、どういった部分が変化し、そしてそれらがお子様や保護者の皆様に対してどのような影響を及ぼすのか、具体的に説明をしたいと思います。
「令和6年度の報酬改定で行われたこと」
① 福祉事業所で得られる報酬単価が全体的に下がった
その他にも何点かあるのですが、上記の2点が一番大きな変化となります。先ずは①「報酬単価が全体的に下がった」ことについて、事業所側と利用者様側にどのような影響があるのかを考えていきます。
「報酬単価が下がるとどうなるのか?」
今年度から児童発達支援・放課後等デイサービス共に、一部の例外はあるものの多くの福祉事業所で受け取ることができる基本報酬(お子様一人に対する一回の支援料金)の単価が下がりました。その背景として、今まで1回1時間の支援を行っても3時間の支援を行っても、事業所が国から受け取れる報酬単価は同じだったため、そこに国のメスが入り、今年度から「長時間の支援を行ったところは基本報酬を優遇しよう」となったわけです。そこで今年度から支援時間による区分が設けられ、30分以上の支援<90分の支援<180分の支援の順に報酬単価が引き上げられました。そのため、以前から長時間の預かり支援等を行っていた一部の事業所にとっては恩恵を受けられたものの、それ以外の事業所にとっては前年度よりも基本報酬が下がってしまい、今まで基本報酬+αで取得できていた未就学児童の個別サポート加算の実質廃止、小学生は土日祝、長期休業日等で得られていた休業日加算の廃止等で約1割~2割程度下がってしまうため死活問題となってしまったわけです。
つまり「事業を存続させたいなら、長時間支援を行えば単価は保証しますよ。でも、短時間支援で続けるなら単価は少ないけど我慢してね」というのが、国の意向になります。その結果として、冒頭で述べた療育大手のL社は今まで個別支援を専門としていましたが、今年度から送迎あり長時間預かり支援の方向に舵を切りました。ここまで事業所の変化について述べてきましたが、次は利用者様への影響を考えていきます。
「報酬減による保護者への影響について」
上述のL社を例に福祉業界の流れを確認したいと思います。
(1)時間区分が導入された事により、報酬単価の低い個別の支援事業所の採算が取れず、事業形態が変更もしくは撤退していく。
(2)多くの児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所が1回90分以上の預かり型の事業所が主な形態となるため、小規模な学童的支援、見守り等が主流となり、個の支援やニーズに対して対応が後手となる。
(3)突発性、衝動性のある児童やコミュニケーション上の課題を抱えた児童等、少人数であっても生きづらさを抱える児童らが安定して通える受け皿が少なくなっていく。
(4)数少ない個別の支援事業所に個別の支援を求める保護者が殺到するも、一回に多くの人数を受け入れることが難しい個別支援の性質上、何年にもわたる待機を余儀なくされ、本当に必要な支援を受けられないお子様が増えていく
保護者に及ぼす影響として、共働き等で長時間預かりを必要とする保護者にとっては事業所選びの幅が広がるため、恩恵を得られる機会が増えました。しかし、預かり型の事業所では多人数の中で長時間過ごさなければならない関係上、お子様によっては安心できる居場所となりづらいことや、お子様の障害特性等によっては利用を断られるケースもあります。一概に全てがそうとは言えませんが、個別の支援を必要とする保護者様にとっては今回の報酬改定は逆風となる場合が多いです。
「個別支援計画と5領域の関連について」
次は、②「個別支援計画における5領域の紐づけの義務化」について解説していきます。先ず、療育における5領域とは「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」が該当します。(児童発達支援ガイドライン参照)
国の言い分は「あなたの事業所で出している個別支援計画に、この5領域はちゃんと関連していますか? してなかったら今後は児童発達支援や放課後デイの事業所として認めませんよ」と言っているわけです。
この背景として、この数年間の間に、民間の児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所の数が非常に増えました。そのため急激に数が増えた分、必要な指導員の数や資質が揃わない状態で運営をするような質の低い事業所や、療育的な支援を行わず「長時間テレビやDVDを見せて預かるだけ」「絵画や体操、音楽遊び等の集客のための習い事で終わってしまっているだけ」の事業所等、悪質な問題が多く挙げられました。
児童発達支援・放課後等デイサービスは根本的には税金事業であり、利用料金が保護者負担は原則1割、国の負担が9割となっております。
そのため、国としては質の低い事業所や習い事等に偏重した事業所は今後少しずつ排除し、5領域の専門的な支援の指標や内容を盛り込んだ個別支援計画になっているかを篩にかけていき、各事業所の質の向上を図ることが今回の個別支援計画と5領域を紐づけることの義務化のねらいです。
つまり「体操だけ」「プログラミングだけ」「絵画やリトミックだけ」行っている事業所は、国の税金を使うのではなく、「これからは正規の利用料金を保護者から徴収して民間の「習い事」事業としてやってください」ということになります。
「個別支援計画と5領域義務化の影響について」
ではこの5領域紐づけの義務化が保護者の皆様にはどのような影響を及ぼすのか、端的にまとめると「習い事系の事業所の数が減るため、事業所選びの幅が狭くなる」に尽きます。今までは国の審査基準が緩かったこともあり、例えば民間の子供向けのプログラミング教室と放デイのプログラミング教室の差異はほぼ皆無でした。そのため、保護者としても通常の習い事であれば週に1回で月1~2万円程度かかる月謝が、放課後デイであれば週に2,3回通えて、かつ一般家庭であれば月額4600円の上限負担額で通うことができます。
料金も通う頻度も比較すると、放課後デイで利用を行えれば費用も格段に抑えることができ、非常にお得と言えます。また、事業所としても保護者負担が1割で、残りの9割が国から補助金として徴収できるため、保護者からの取りこぼしもなく、収益を安定して確保できるため、療育に民間事業が参入できるとなった段階で、各事業所が集客のため体操や水泳、絵画、リトミック、プログラミング等の子どもに人気な習い事に走ることは必然の流れでした。
「まとめ」
今回、報酬改定を巡る児童福祉業界の変化と保護者様への影響について、まとめさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。国としては予算削減のため、年々増加の一途をたどる児童発達支援・放課後デイ事業所を報酬改定や5領域の紐づけによる義務化によって、現在の質の低い事業所の数を篩にかけ、また、今後の新規事業参入のハードルを上げる事で対策を講じたいのだと思います。
個人的な感想になりますが、今回の報酬改定は、現在蔓延っている質の低い事業所も本来地域にとって必要な支援を行っている事業所も一緒に押し流しかねない強引さを強く感じました。
個別は個別、小集団は小集団のそれぞれの支援が出来るお子様の層が違うため、国が支援時間によって優劣をつけてしまえば、バランスは崩れます。その結果、L社のように方針転換をする事業所が増えていき国が目指す「多様性の尊重」や「個のニーズに応える支援」とは真逆の方向に向かっていきます。
新設された子ども家庭庁の予算が6兆4000億円もある中、放課後デイ等にかかる予算が約3500億円程度(令和元年度データ参照)と考えると、全体の5%程度にしか過ぎません。もちろん、不必要な費用は削減し、適切に事業所の見直しを行っていく必要があると思います。しかし、その見直す基準が「支援時間の長短」と「個別支援計画と5領域の紐づけ」では今回のように福祉業界全体が混乱し、必要な支援を求める需要の層と供給の層が釣り合わなくなってしまいます。
「何をもって質の高い療育とするか」は非常に難しいテーマではありますが、有識者だけの机上の議論ではなく、福祉の現場の意見も十分に取り上げた上で適切な指標が定まってほしいと思います。
その上でお子様にとって本当に必要な支援を行っている事業所は短時間であっても正しく評価をされる仕組みを作って欲しい、と一事業所の経営者として切に感じております。
ご利用に関する疑問や質問などありましたら、お気軽にお問い合わせください。