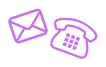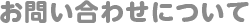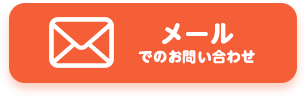公認心理師がいる教室

先日ニュースで、東京都の教員採用試験で小学校教諭の受験倍率が定員割れ寸前の1.1倍と報道されました。以前から各都道府県で小学校教諭の受験者数が減り続け、定員割れを起こす自治体が増えているとちらほら報道されていましたが、とうとう東京都も深刻な人手不足(成り手不足?)の波が押し寄せてきました。
そもそも、公務員という魅力的なステータスでありながら、なぜここまで小学校教諭は不人気な職業となってしまったのでしょうか。私自身が担任だった頃を振り返りながら解説したいと思います。
① 終わりの見えない長時間労働
これが第一に敬遠される理由だと思います。地方公務員であるため、名目上は1日9時間労働(休憩時間45分)のため、一般的に8時~17時が勤務時間となっています。しかし、当然のことながら、朝の8時には子ども達は校門の前に集まり、登校してきます。そうなると当然始業時間の8時より前に管理職をはじめ、先生方は勤務を始めています。(私は朝7時出勤でした)
そして、休憩時間の45分ですが、これはあってないようなものです。原則、学級担任を持つと給食の時間は休憩ではなく指導時間です。30人からなる集団をトラブルなく時間内に食事をさせようと思ったら、担任はゆっくり食べたり、味わったりする余裕など皆無です。では、子ども達の下校後、16時以降はどうかというと、この時間帯に職員会議等が度々入ります。私の小学校では16時~16時45分が休憩時間という就業規則でしたが、職員会議や、保護者対応、回収したノートやテストの添削等があるため、「ちょっと外まで一服しよう、、、」という先生は非常に少数派でした。そのため、担任がようやくホッと一息つける時間は、夕方17時以降のため、この時点で本来であれば勤務時間終了です。しかし、学級担任の仕事はこの17時以降にやっと取り組む事になります。
当時を振り返ると、私は17時以降に翌日の授業準備をしていました。毎日行う国語や算数であれば板書案(ノートに黒板に書く内容の下書きを書くこと)を作ったり、体育であれば、実際に体操や鉄棒等は自分が体を動かして、身体の使い方を確認したり、跳び箱等の用具の安全な取り組み方、グループの班分け等を実際に校庭や体育館に行って考えたりしていました。その他、毎週の時間割表の作成や、ノートの添削、テストの丸付け等を行っていました。
このように自分のクラスのことだけに注力出来れば、19時頃には学校を出ることができました。しかし、ここに学年の行事や学校全体の行事等の業務が定期的に入ってくるため、中々自分のクラスの仕事だけに集中できるわけではありません。例えば、学年で行う発表会や音楽会等の段取りや役割分担、遠足等の校外学習の打ち合わせ、運動会の学年の種目決め、リレー等の配置、等など、例を挙げるとキリがありません。これらの学年、学校の仕事は担任が一人で自分の裁量で行えるものではないため、学年間で相談、協議したり、管理職に事前に稟議書を作成して提出したりする等、非常に時間も手間もかかるものでした。
こういった自分のクラスとクラス以外の業務を常に並行して行うため、当時の私の勤務時間は7時~22,3時の15時間労働が平均でした。毎日、早朝出勤も含めれば6,7時間の残業をしていることになるんですね。月平均130~140時間(土曜出勤も含めれば更に上がります)が残業ということになります。平均的な過労死ライン80時間を軽々飛び越えていきます。私は民間企業に転職して初めて産業医面談は月残業80時間を超えている人のみが受けるものだと知りました。小学校だと先生方が皆一人ずつ呼ばれていたので、必須のものだと思っていました。
今にして思えば、「なんで誰も文句言わないの!?」と考えられるのですが、当時、私の周りの先生方も皆、そのぐらいの時間帯まで残って仕事をされていたので、当時はそれが当たり前だと思っていました。
② 支払われない残業代
さて、これだけ早朝出勤もする、深夜残業もするとなれば「残業代がたくさんもらえて良いじゃない」と、民間企業の友人に言われた事があります。しかし残念ながら、教員に残業代を支払われることはありません。教育公務員特例法という法律の中に給特法(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)というものがあります。これはどんなものかというと、1966 年当時の残業時間が月8時間程度であったことから給料月額の4%相当の「教職調整額」を支給する代わりに、時間外勤務手当および休日勤務手当は支給しなくてよい、という法律です。つまり、「給料の4%分を支払うと、教員を月額何時間でもタダで働かせ放題だよ!」という悪魔のような法律なのです。
私も民間に勤め、その後自分で会社を興して従業員を雇う立場となりましたが、人を一人雇えば当然、人件費がかかります。更に業務上、残業を命じた場合は、時給で言えば125%分を上乗せして支払わなければいけません。休日出勤であれば135%分の上乗せになります。そのため雇用主は従業員がなるべく残業をしないよう、個々の業務を調整したりしてコスト管理をするのですが、学校現場ではその労働の原理が働きません。この給特法という抜け道があるため、現場の管理者(校長や教頭)も人件費というコストの概念がなく、いくらでも残業するのが当たり前、仕事が終わらないのは自己責任、といった風潮が作られてしまうのです。
この風潮は現在でも続いており、妻も小学校の教員ですが、やはり埼玉も神奈川も同じような職場環境でした。管理職が「自分もそのように働いてきた」という意識をそのまま受け継いでいってしまうことが労働環境の負の連鎖を作り続けてしまいます。学校という閉じた環境、閉鎖された社会を変えていくためには、きちんと教員に残業代を支払うことで、管理者が人件費のコスト管理、意識を高めることが不可欠です。この悪魔の給特法が改正されることを切に願います。
③ 新人もいきなり学級担任
個人的には、この制度が若手の先生方の離職率を加速させてしまう一番の要因なのではないかと思います。通常、教員採用試験に合格するとほぼ間違いなく次年度は学級担任を持つことになります。そうすると、大学在学時に教員採用試験に合格した優秀な学生は3月の卒業と同時に4月には教壇に立ち、30人、40人の子ども達を相手に「先生」にならなければいけません。
大学の授業では、各教科の学習指導等はカリキュラムの中である程度触れるものの「集団指導の方法」は教えてくれません。また、これは講義を聞いて身に付くものではないため現場の実践の中で「声の出し方、表情の作り方」「褒める時、叱る時の声掛け」「学級運営のためのルールづくり」等を学んでいく必要があります。私は、大学在学時の教員採用試験は不合格だったため新卒1年目は臨時任用教員として、算数少人数や、図工の専科、特別支援級等の補助をしながら先輩の先生方の学級経営を見たり、授業の一部を行ったりすることで段階的に学ぶことができました。今にして思えば、在学時の教員採用試験に落ちて本当に良かったと思います。新卒1年目で担任外という立場で現場を見て学び、「学級担任はこういう仕事なんだ」という心構えを持つことが出来ました。もちろん、見るのと実際に自分が担任を持つのでは大違いだったのですが、それでも1年の猶予期間は大きく、実際に授業をする際の声出しや、段取りの組み方、子どもを褒める時、叱る時の強弱、緩急のつけ方等、教育実習で学べなかったものをある程度得た状態で2年目に学級担任を持つことができました。
これが新卒で担任を持った先生の場合、右も左も分からない状態で学級担任としてスタートし、手順や勝手が分からないことがあってもクラスを置いて聞きに行くわけにもいかず、一人で初めてのことを捌いていかなければいけません。それは授業の説明や指導、給食を子ども達だけで配膳させる指示、子ども同士のトラブルの指導、保護者対応等、その場で起きることに対して自己裁量で臨機応変に動かねばならず、またその一挙手一投足を大勢の子ども達はよく観察しているのです。当然、初めて担任を持つ先生がベテランの先生と同じように仕事が出来るわけでなく、同じ教科の指導、全体指示等をとっても綻びや指導しきれない部分が出てくるため、一部の子ども達がその間隙を突いて、指示に従わなかったり、ルールを破ったりする等、クラスを崩しにかかってきます。
ベテランと新人では学級運営に力量差があるにも関わらず、学級担任は同じ仕事、責任を背負って取り組まねばなりません。また1日中、基本的に担任一人でクラスを見ていかなければならないため、困った場面があっても隣が授業をやっていたらヘルプも出せず、孤独な闘いを強いられます。以前の勤め先で新卒の先生と産休明けのママさん先生の2人で3年生を受け持つ年がありました。ママさん先生が主任で新卒の先生に一生懸命教えてくれるのですが、お子様の送り迎えがあるため5時には職場を出なければならず、新卒の子は夕方以降にクラスのこと、授業のこと等を相談したくても相談できない日々が続きました。そのため、毎日遅くまで残った先生方がサポートをしてくれてはいたものの、ある日「クラスの子ども達に指導するのが怖い」と、そのまま出勤できなくなってしまい、2学期の中旬、志半ばで退職することとなりました。
夢を抱いて勉学に励み、晴れて教員採用試験に合格しても、過酷な現実に打ちのめされ、泣く泣く教育現場を去る若い先生方が大勢います。その要因はやはり、大学で学ぶ内容及び教育実習と実際の教育現場で行うことのギャップが大きすぎるからです。教科指導と学級経営は全く別物であり、クラスが健全に運営されて初めて国語や算数等の教科指導が活かされます。よく「分かる!楽しい!授業が子ども達を育む」と言われていますが、誤りがあります。それは「授業中の指示を聞ける子ども達」が前提であるからです。授業中の指示が聞けない、いわば学級運営が正常になされていないクラスには、教材準備を入念に行い、どれだけ良い授業をしたところできちんと内容を理解し、楽しめる子ども達はごく僅かでしょう。小学校の先生が自分の抱いた理想を、夢や希望を持って授業をしていくためには、その前段階に集団の指導ができること、集団を束ねられることが必要になります。
私が思うに、新卒1年目の先生は担任を持たず、様々な学年の先生の授業アシスタントや、図工や理科などの一部教科の指導を分担する等、実際の授業や生徒指導の様子等を見て学ぶ時間、実際に一部授業を行うことで教壇に立つ練習を十分に取るべきだと思います。それほどに大学で学ぶことと現場のギャップは大きいからです。しかしながら、現在の教育現場では臨時任用教員ですら学級担任を持たされ、どの自治体も人材不足のため、新人を担任外として丁寧に育てる余裕がない現場がほとんどでしょう。
その結果として、教員志望者が更に減り、教員の数が減ることで現場の負担は増え、ただでさえ少ない現場の人員が病休等で抜けていくという悪循環が形成されます。逆説的に考えれば、教職員の数を増やすことで現場の負担を減らし、また職員に残業代等を適切に支払う事で待遇改善を行えれば、教員という仕事にメリットや、やりがいを見出して志望者が増える、という生の循環をつくることができますが、そのためには文科省や国が本腰を入れて介入しなければ、まず不可能です。先日ニュースで、「教員不足対策に5億円の補正予算を盛り込む方針」と報道されましたが、その内容が教職に興味がある人や教員免許をもつ人に対してイベントを行う、民間企業で働く免許保有者が期限付きで教員として働けるようにする等の、対策と方針のピントがずれたものばかりでした。まだまだ、小学校の現場に変化の兆しや、夢や希望を持って働けるようになるには時間がかかりそうです。
ご利用に関する疑問や質問などありましたら、お気軽にお問い合わせください。