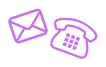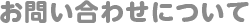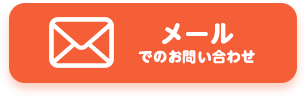公認心理師がいる教室

質問④ 就学後の学習は先取りで予習した方がよいか
お子様が初めて学習する事に不安を覚えたり、学習の見通しを持たせることで落ち着いて過ごせるのであれば一定の効果はあるかと思います。
ただ、過度な先取り学習(1年生の段階で2年生の掛け算や3年生の割り算等の計算に取り組ませるようなこと)は推奨しません。例えば、掛け算や割り算等、計算の仕組みさえ覚えてしまえば練習量次第でより早く、正確に計算することができるようになり、計算問題を多く解くことがお子様の自信に繋がります。しかし、それはあくまで処理としての計算が出来るだけであって掛け算や割り算の本質を理解している訳ではありません。そのため、計算問題は出来ても掛け算や割り算のちょっと複雑な文章問題を読み解いて立式したり、自分で文章問題を作ることは出来ない、分からないといった、アンバランスな状態となってしまいます。
私が2年生を担任していた時に、掛け算の授業で「もう塾で習った」「進研ゼミでやったから分かる」といった子ども達がいましたが、自分が「分かる」ことに慢心し、初めて掛け算を学ぶ子ども達よりも明らかに「学習態度が良くないなー」と思ったことを今でも覚えています(笑)
子ども達にとっては「初めて学ぶこと」というのはとても新鮮な体験であり、初めてだからこそ緊張感をもって、集中して取り組む事ができます。しかし、先にやる内容が分かってしまうと興味や関心も半減してしまい、新鮮味も薄れてしまいます。これは我々大人が映画等を観賞する際に先にネタバレを知ってしまうイメージに近いかと思います。また、中途半端に「分かる」経験が先行してしまうと、なまじ先に学習したプライドがある分、途中でいざ問題が難しくなった時に素直に分からない事を質問することを難しくしてしまいます。これは他の学年でも同様の様子が見られました。そのため、お子様の特性を鑑みて、少しの先取り学習であれば取り組む価値はあるかと思いますが、大幅な先取り学習はあまり推奨する立場ではありません。
質問④ 就学後の学習は先取りで予習した方がよいか
(つみきでの放課後デイの学習のあり方についての周知)
 こちらは質問の回答ではなく、この教室の小学生の学習指導の在り方についてお伝えできればと思います。つみきの小学生以上の学習指導では「民間で行う支援級」をコンセプトとしており、「繰り返しによる積み重ね」を重視して取り組んでいます。「読み」「書き」「計算」の復習、習熟を主としてお子様の実態に合わせて支援方法を考えております。
こちらは質問の回答ではなく、この教室の小学生の学習指導の在り方についてお伝えできればと思います。つみきの小学生以上の学習指導では「民間で行う支援級」をコンセプトとしており、「繰り返しによる積み重ね」を重視して取り組んでいます。「読み」「書き」「計算」の復習、習熟を主としてお子様の実態に合わせて支援方法を考えております。
国語では、文章を読み取りの他、特に「書くこと」に力を入れております。「書く」内容では主に作文指導を通じて、自分の経験したことや思ったことを筋道立てて伝えられることを目標にしています。ひらがな、カタカナ、漢字の書き取り等はある程度一人で練習できる分野ですが、作文については文章の構成や、添削等、大人のサポートが必要になる部分が多いため、どの学年でも学習内容に取り入れて行っております。
算数では、お子様の学年に応じた「四則計算(足す、引く、掛ける、割る)」の計算の習熟の他、「文章問題のイメージ化」ができることを目標に支援内容を考えております。四則計算では、今後の生活の経験の中で扱う計算がある程度の暗算ができるように、繰り上がり、繰り下がりの計算や100マス計算等で達成感や肯定感を高める練習を行います。文章問題では、読んだ文章を図に書くことでイメージできるように練習し、説明ができるように取り組むことでそれぞれの計算の本質が理解できるよう促します。
つみきの学習支援は、学習塾のような先取り学習を主としたものではなく、繰り返しの学習が続くため、地味で単調な作業に見えるかと思います。しかし、私が大事にしたいことは地味なことをコツコツと取り組める粘り強さと、国語なら国語の、算数なら算数の学習の本質をイメージして取り組める理解力になります。何卒、教室の支援にご理解ご協力いただければ幸いです。
ご利用に関する疑問や質問などありましたら、お気軽にお問い合わせください。